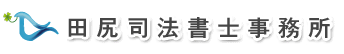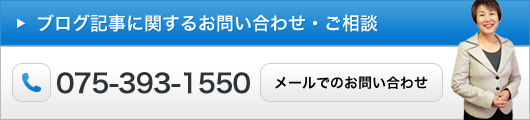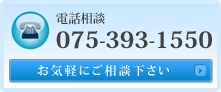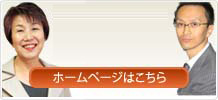遺言書に係わる紛争を防止するために②
前回のブログで遺言の内容面で相続人間で問題が生じることがあるとお伝えしました。
では、具体的にどのようなケースが遺言書があっても、相続時に問題が生じるのでしょうか?
①遺言者よりも先に受遺者が死亡した。
遺言を書いた人(遺言者)よりも先に、遺産を受け取る人(受遺者)が亡くなった場合、
遺言はその限度において効力を生じません。
例)甲さんが死亡したとき、Aさんに土地(京都市西京区山田四ノ坪町1-6)を、Bさん
に有価証券を相続させる遺言をした。
Aさんが交通事故で死亡したあと、甲さんが死亡した。
→ この場合、原則的にはAさんに土地を相続させる遺言は効力を生じなくなり、土
地は甲さんの相続人が相続することになります。
甲さんは、仮にAさんが甲さんより先に死亡していた場合についての遺言内容を記すことで、上記のような事態の回避を考えておくことがいいと思われます。
次回も具体例についてです。